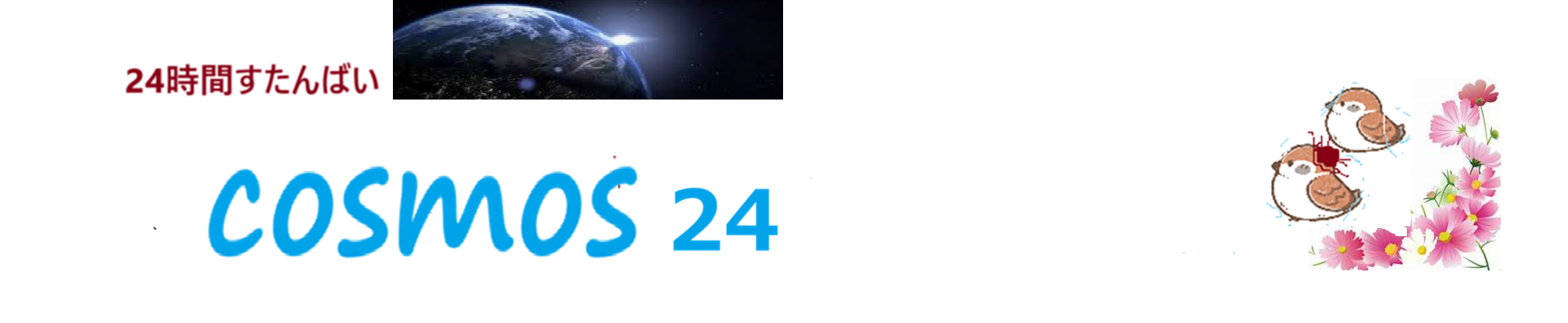長く生きてきましたが、
あれほどたくさんのホタルを見たのは、後にも先にもあの時だけでした。
見たというより、体験したというほうがちかいかもしれません。
祖父が、17歳で宮大工の徒弟になって、親のつくった借金返しから始め、一代で、金沢のその小さな町内では一番の資産家となったのに、その資産を蕩尽しつくした父が、
母と15歳の姉を頭にひとまら5人の子をともない、一家7人で、北陸・金沢から東京へと越す前夜でした。
あの夕べ、暮れきるにはすこし間のあった金沢の浅野川の川原を、おびただしい数のホタルが飛び交った光景は、70年の長い時を経ても、ひとまの目につよく焼きついて、今日まで薄れることはありませんでした。

上京前夜、浅野川で見たホタルは…
少年の背で、頭上まで視界いっぱいのホタルを見ていました
暮れはじめた浅野川の川原は、5歳のひとまの目にとても広く見えました。
川原には一面草が生いしげり、川面はほとんど見えなかったような気がします。
弱まりつつある光の加減で黒っぽく見える草の間から湧き出るように、はかない光の尾を曳きながら無数のホタルが舞い立ち舞いもどり、頭上の暮れかけた空いっぱいに、飛び交っていました。
町中の川原です。
音がしていたはずですが、そのときの風景に音の記憶はありません。
ただ、頭上まで視界いっぱいに、ゆっくりと乱舞するホタルの曳く無数の光に目もこころも奪われていました。
ひとまは瘦身の少年の背に負われていました。
なんの不安もなく少年の肩に両腕をまわし、負われていたのです。
ホタルはたびたび、ひとまのほほや鼻先までかすめて飛びました。それがとても快くおもえました。
少年の背でホタルの群舞を見ているひとまは、
これから暮らす東京のことも、これまで住んでいた薄暗い土蔵での生活についても、なんの思いもありませんでした。
ただひたすら、おびただしいホタルが描く光の曲線の交差するさまを、飽きもせず見ていました。
少年は後年検事に?
後年、姉たちに聞いた話では、父が家産を失う前から懇意にしていた職業不詳の「おじさん」が、東京へ出る父とその家族のために、その夜、つましい小宴をととのえてくれたということでした。
少年はおじさんの次男で、その時は15歳くらい。
長じて自衛隊で働きながら学び、司法試験に合格。
その後、弁護士ではなく検事になったと聞いたようにおもいます。
下の姉とは文通していたようですが、いつのまにか、疎遠になったようです。
その後父は、小さな繊維問屋の経理として努め終えた後、再起を目指しましたが果たせず、70歳で人生を終えました。
金沢・浅野川には、いまも、季節になれば、あんなにもたくさんのホタルが飛ぶのでしょうか?
ひとまは、ホタル飛ぶ季節の浅野川を、いまだに再訪できません。
荒川区尾久の小さな家
翌日、父とともに、一家は、東京への汽車に乗りました。
何時に乗ったのか時間はおぼえていません。
記憶では、3等車の黄みがかった明かりに照らされた夜汽車内で、幼かった3歳の弟と5歳のひとまは、二人分の座席スペースに寝かされていました。
ときどきトンネルに差しかかると、汽車の煙を避けるため、ひとまの家族をはじめ乗客たちがあわてて窓の鎧戸をバタバタと降ろすのでしたが、すると黄色い灯りがすこし際だって、薄暗く照らされた車内は、子ども心にみょうにわびしく感じられました。
父は、東京・荒川区尾久の路地奥の狭い借地に、小さな家を建ててありました。
畳1枚弱の玄関を入ってすぐが半間の押入れがついた3畳、その右手奥が4畳半一間(ひとま)で、一間(いっけん)の押し入れがありました。
その奥が板の間と土間あわせて3畳にたりないくらいの台所で、トイレ、というより便所は、70年むかしはごくふつうだった汲み取り式。
庭は、いうまでもなく猫の額ほどで、裏の家との間を低い生垣で仕切られていたように思います。
まるでおままごとの家みたい!
その家に着くなり、ひとまは、くつも脱がず、玄関のあがりがまちから腹ばいになって、右手、台所の方をのぞき込んで、うれしくなりました。
襖や障子など、あいだの建具がすべて引きあけられていたので、そこからまっすぐ、その小さな庭(というより、奥の隣家と接した隙間のような土地にすぎないのでしたが)までが、ひとめで見通せたのです。
(まるでおままごとの家みたい!)そう思い、うれしかったのでした。
それまでの金沢での家は広く薄暗く、とうてい玄関から中庭まで見通せなかったし、厠(かわや・トイレのことです)も中庭に面した屋外で、子どもには、怖かったのです。
腹ばいになった真新しい畳からは、イグサの良い匂いもしていました。
そのときの幼いひとまに、そのあとにつづく貧しい生活が自分にどんな運命をもたらすかなんて、知るはずもありませんでした。
ともあれ、こうして、マッチ箱みたいな家で、親子7人の東京での貧しい暮らしが幕を開けたのでした。
短歌
ふるさとをはなれる明日知らぬ夕べ
無数のホタル舞うを見にけり

30代のひとまの父 抱かれてる赤ちゃんは不明。

20歳くらいのひとまの母
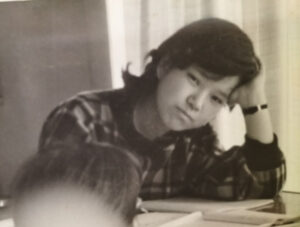
17歳のひとま。同い年の高田美和さんの「17歳は一度だけ」という歌がヒットしていました。
数十年ぶりで見た自分の写真に、(そういえば、こんな顔していたなあ、むかしは!!!)…と。
若さは風と共に去っていきました……。
なぜか、加齢とともに、父にどんどん似ていくひとま…。
まあ、父の子なんで当然ですが。
写真はもう撮られたくないですヾ(。>﹏<。)ノ。
ラジオ

昭和30年ごろのラジオhttp://www.dokidoki.ne.jp/
台所にいると、裏隣のラジオが聴けました
金沢から荒川区の小さな家に引っ越してからしばらくの間、
わが家にラジオはありませんでした。
いつからか、5歳のひとまは、
ラジオを聴くために、家人のいない台所に行くようになりました。
裏どなりの家のラジオが、台所にいるとはっきり聞こえたのです。
ニュースや、ラジオドラマ、童謡も聞こえましたが、流行歌がいちばん多かったように思います。
こうして、ひとまの音楽との出会いは、歌謡曲からはじまりました。
気の利いた家の子どもなら、ピアノでも習い、童謡やクラシックに親しむ年ごろに、ひとまは、大人の流行歌に聴き惚れていました。
もちろん、ほんとうは童謡のほうがずっと好きでしたが(クラシックは、その当時、存在さえ知りませんでした)、
「裏どなりの家のラジオ」からは、めったに童謡は聞こえてこなかったのです。
あるとき、いつものように、ラジオで覚えたての流行歌を、ひとり、いい気分で大声で歌っていると、
いつの間にかすぐそばに、母がきて立っていました。
見上げると、困惑した顔で、
「コレッ、そんなうたうたっちゃだめ!」といいました。
そのとき5歳のひとまが歌っていたのは、「トンコ節(ぶし)」でした。
トンコぶし
トンコ節
作詞 西城八十
作曲 古賀政男
歌 久保幸江
あなたのくれた 帯どめの
達磨の模様が チョイト気にかかる
さんざ遊んで ころがして
あとでアッサリ つぶす気か
ネー トンコ トンコ
言えばよかった ひと言が
なぜに言えない 打明けられない
バカな顔して また帰る
恋はくるしい 朧(おぼろ)月
ネー トンコ トンコ
以下ウイキペディアから引用
「トンコ節」(とんこぶし)は、1949年1月に久保幸江と楠木繁夫のデュエットとして日本コロムビアから発売された曲。また1951年3月に同じく久保幸江が新人歌手であった加藤雅夫と共に吹き込んだ新版の曲。
1948年に発売された『炭坑節』のヒットをヒントに、作曲家である古賀政男が民謡調の唄でより都会的センスを持つ曲を作ってみようと思い立ち、「タンコ」を「トンコ」にすることを思いつく。
しかし久保幸江と楠木繁夫により歌われた『トンコ節』は発表当時ヒットすることはなく、それを受けて久保幸江は全国を巡り営業先のステージで歌うことに努め、1950年の夏頃から51年にかけて流行りだす。
その結果コロムビアは1951年3月に改めて新版を出すという事態に至り、大々的なPRも功を奏して全国を風靡した。なお新録音の時は、楠木繁夫が退社していたので、新人の加藤雅夫と久保幸江が吹き込んだ。
1950年以降から売れ出した理由には朝鮮戦争の特需景気による「お座敷の繁盛」という社会状況の変化が大きかったともいわれ、歌詞に見られる「さんざ遊んでころがして」や「上もゆくゆく下もゆく、上も泣く泣く下でも泣くよ」といったアブナ絵的な文句が、特需景気で増えた新興成金層による宴会などで騒ぐためのお座敷ソングとして定着したことが大きな要因とされている。
新版を発売するにあたりコロムビアは、引き続きの作詞者である西條八十に対して「宴会でトラになった連中向きの唄を」と依頼しており、それに応える形で八十は当時としてはエロ味たっぷりの文句に書き直した。
評論家の大宅壮一はこれを「声のストリップ」として批判している。
1952年には、ブラジルのトリオ・マドリガル(ポルトガル語版)が「私の甘い愛」の意味の曲名でポルトガル語でカバーした。
「自分」は、絶対の存在だと思っていました
5歳だったあるとき、ふと、ふしぎに思いました。
(どうして3歳のころより前のことを思い出せないのだろう…)と。
そのとき、ひとまは、「ひとまという自分」が、限られた命を与えられている、ごくはかない存在に過ぎないことなど、まったく知りませんでした。
「自分」は、無限のむかしから無限の未来まで存在しつづける、絶対の存在だと感じていたのです。(もちろんこんなむずかしい言葉で考えたわけでなく、そう感じ、思い込んでいただけですが…)
人が、母親の胎内に宿ったときからはじまり、およそ10か月を経て生まれ、その後さまざまな器官とともにできあがっていき、記憶をつかさどる機能がようやく働き始め、そこにいたって初めて、「自分の過去」が集積されるのだということなど、
5歳のひとまは、知るはずもありませんでした。
「自分」という存在が、ず~っとむかしからあり、この先もず~っと永遠に続くものだと思いこんでいたひとまは、
あるとき、「自分のむかし」「ず~っとむかしからの記憶」を思いだすことにしました。
意識を集中して、しっかり考えれば、きっと思いだせると思ったのです。
手のひらを固くにぎった両腕をぎゅっと体にひきつけ、目を閉じ、意識を集中しました。
あんまり集中して、すこし頭が痛くなるまで続けました。
けれども・・・、もちろん思いだせませんでした。
ふしぎで、ふしぎで、なりませんでした。
でも、そのふしぎについて長く拘泥することはありませんでした。
5歳のひとまの前には、毎日、つぎつぎにあらたな体験が、波のように絶えまなく押し寄せていたのです。
たった一つの疑問に、拘泥している暇なんてなかったのです。
ただ、そんな疑問を持ったことだけが、潮が引いた後にのこる貝がらのように、記憶に残りました。
そして、ひとまも、いつのころからか、ひとが、「生まれてから始まる存在」なのだと、知るようになっていました。